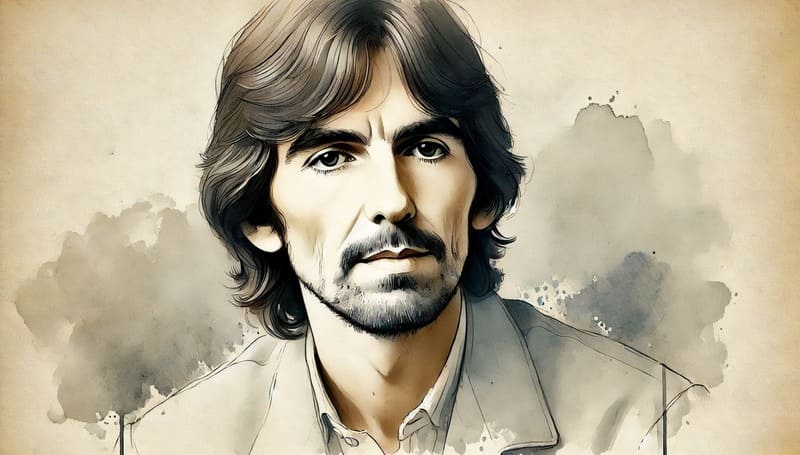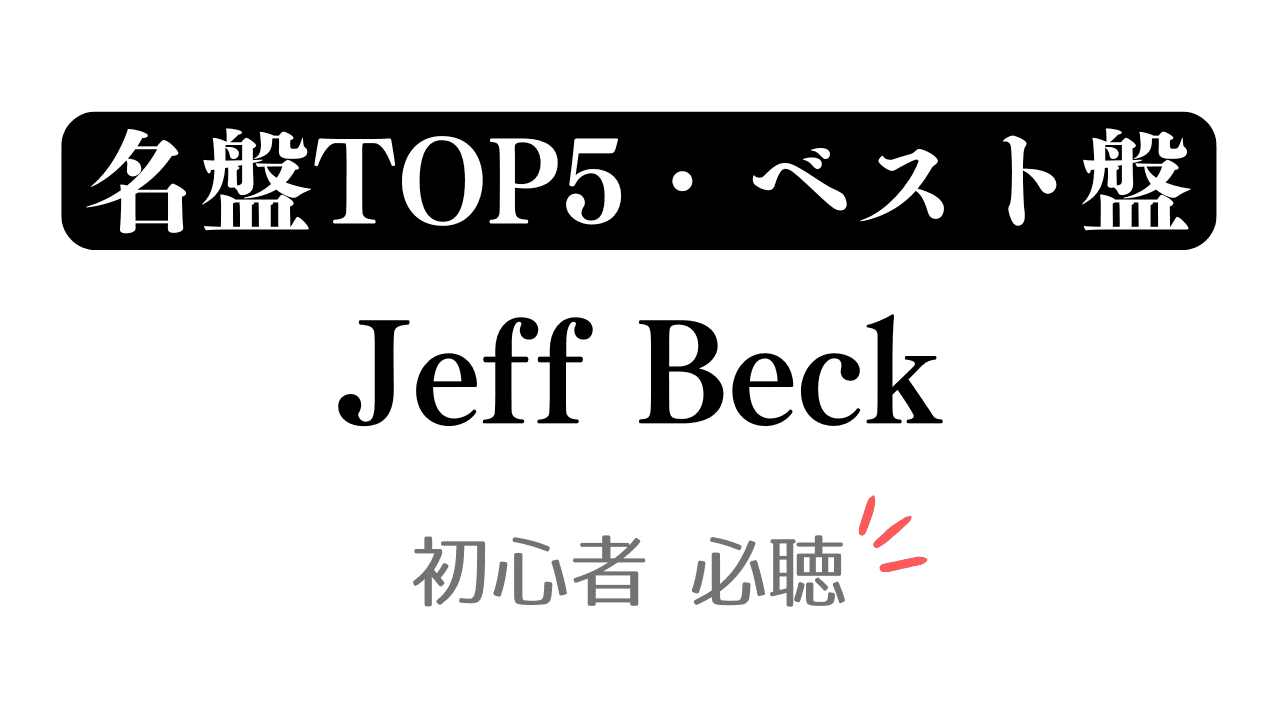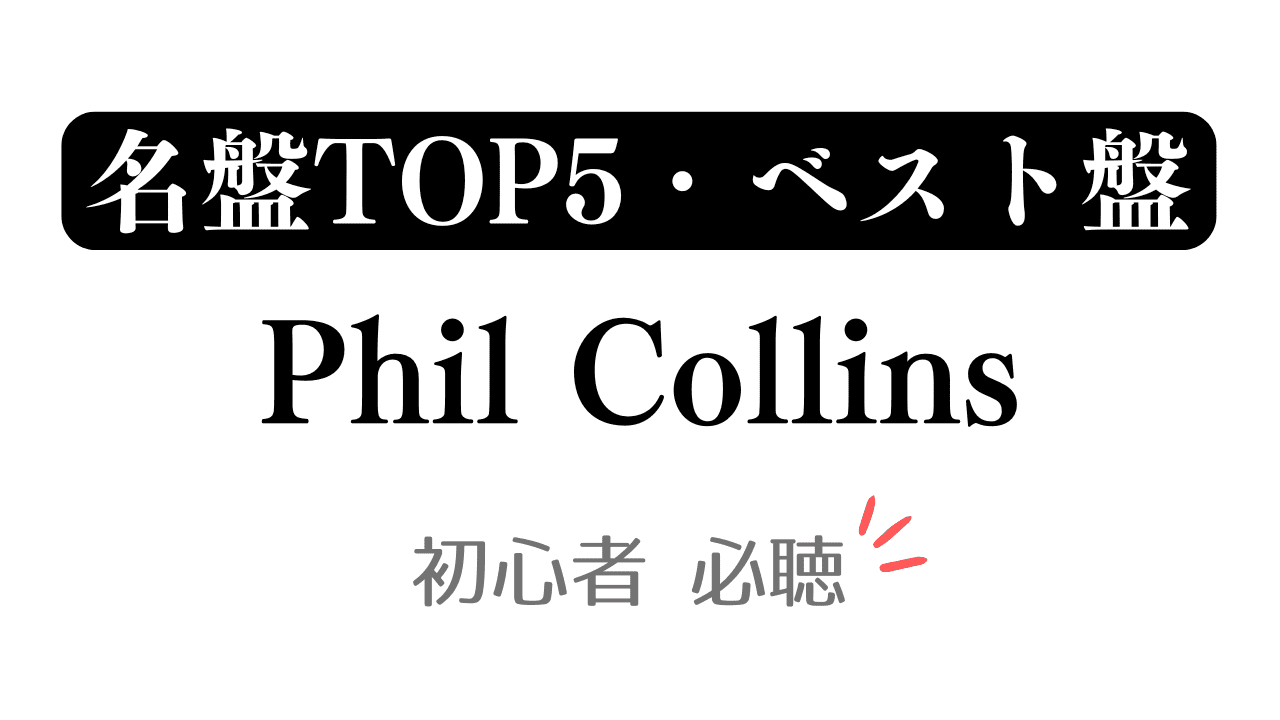1964年、ロンドンの小さなパブで4人の若者が奏でた激しいサウンドが、ロック史の扉を開いた――。
西ロンドンの労働者階級から生まれたザ・フー(The Who)は、楽器を破壊し、爆音で観客を圧倒し、「ロックンロール・サーカス」と呼ばれる伝説的なライブパフォーマンスで音楽界に革命を起こした。ピート・タウンゼントの天才的な作曲能力とロジャー・ダルトリーの魂を揺さぶるボーカル、ジョン・エントウィッスルの重厚なベースライン、そしてキース・ムーンとケニー・ジョーンズの躍動するドラムが織りなすサウンドは、ハードロックからプログレッシブロック、さらにはパンクロックまで、現代音楽のあらゆるジャンルの礎となった。
「My Generation」で反抗精神を歌い上げ、「Tommy」で世界初のロック・オペラを完成させ、「Won't Get Fooled Again」で政治への不信を表現した彼らの音楽は、単なるエンターテインメントを超えた社会現象となった。楽器破壊パフォーマンス、マーシャルアンプの壁、そして伝説のウッドストック出演――すべてが音楽史に刻まれる記念碑的な出来事となっている。
半世紀を超えるキャリアで生み出された数百の楽曲から、21曲を厳選してお届けする本記事では、ザ・フーの音楽的進化を時系列で追いながら、それぞれの楽曲が持つ革新性と影響力を深く掘り下げていく。初めてザ・フーの世界に触れる人にも、長年のファンにも、新たな発見と感動をお約束しよう。
ロック史を変えた永遠の代表曲
My Generation ~若者の反抗を歌った永遠のアンセム
1965年10月にリリースされた「My Generation」は、ザ・フーの代表的な楽曲であり、60年代の若者文化を象徴する不朽のロックアンセムです。「I hope I die before I get old(年を取る前に死にたい)」という衝撃的な歌詞は、当時の若者たちの既存の価値観に対する反発を代弁し、世界中の若者の心を掴みました。
ジョン・エントウィッスルの革新的なベースライン、ピート・タウンゼントのつんざくようなギターリフ、そしてロジャー・ダルトリーの情熱的なボーカルが生み出すエネルギッシュなサウンドは、それまでのポップスとは一線を画す新しい音楽の形を提示。現在でも反体制の象徴として多くのロックバンドにカバーされ続けています。
Won't Get Fooled Again ~政治への不信を歌った反骨精神の傑作
1971年6月、アルバム『Who's Next』からのシングルとして発表された「Won't Get Fooled Again」は、政治的権力への不信と反抗を歌った壮大なロック叙事詩です。8分を超える長編楽曲でありながら、キーボードシンセサイザーを効果的に使用した当時としては革新的なアレンジで多くの批評家から絶賛されました。
「Meet the new boss, same as the old boss(新しいボスに会おう、前のボスと同じだけど)」という皮肉に満ちた歌詞と、ロジャー・ダルトリーの魂を込めたボーカル、特に楽曲終盤の伝説的な絶叫は、ロック史上最も印象的なパフォーマンスの一つとして語り継がれています。
Baba O'Riley ~シンセサイザーとロックの完璧な融合
1971年、同じく『Who's Next』に収録された「Baba O'Riley」は、ピート・タウンゼントが作り上げたシンセサイザーのリフと、バンドの圧倒的な演奏力が見事に融合した革命的な楽曲です。インド哲学者ミーハー・ババとミニマル音楽の作曲家テリー・ライリーへのオマージュとして名づけられたこの楽曲は、プログレッシブロックの代表作として位置づけられています。
開始から響く印象的なシンセサイザーのアルペジオは、現在でも多くのアーティストに影響を与え続けており、映画やTVCMでも頻繁に使用される現代音楽の古典となっています。
Behind Blue Eyes ~内面の孤独を歌った美しいバラード
1971年、『Who's Next』に収録された「Behind Blue Eyes」は、ザ・フーのレパートリーの中でも特に美しいメロディを持つバラードです。外見とは裏腹な内面の孤独と苦悩を歌ったこの楽曲は、ピート・タウンゼントの作詞・作曲能力の高さを示す代表作となっています。
アコースティックギターから始まり、徐々に壮大なアレンジへと発展していく構成は、多くのロックバラードの手本となり、リンプ・ビズキットをはじめ数多くのアーティストにカバーされ続けています。
Love, Reign O'er Me ~愛への渇望を歌った壮大な名曲
1973年のロック・オペラ『Quadrophenia』のクライマックスを飾る「Love, Reign O'er Me」は、愛への切実な渇望を歌った感動的なバラードです。ロジャー・ダルトリーの感情豊かなボーカルと、オーケストラルなアレンジが印象的なこの楽曲は、ザ・フーの音楽的成熟を示す重要な作品として評価されています。
雨の中で愛を求める主人公の心境を描いた詩的な歌詞と、ピート・タウンゼントの美しいギターソロが織りなす芸術性の高い楽曲として、現在でも多くの音楽評論家から高く評価され続けています。
爆音で会場を揺らすハードロック・ナンバー
I Can See for Miles ~サイケデリック・ロックの金字塔
1967年10月にリリースされた「I Can See for Miles」は、ザ・フーがサイケデリック・ロック時代に生み出した革新的な楽曲です。当時としては非常に実験的なサウンドプロダクションと、ギャンギャンにディストーションを効かせたギターサウンドで多くのミュージシャンに影響を与えました。
全米チャートで9位を記録し、ザ・フーにとってアメリカでの最大のヒット曲となったこの楽曲は、後のハードロックやヘヴィメタルの発展に重要な役割を果たした記念碑的作品として評価されています。
Magic Bus ~ポップセンスとロックパワーの絶妙なバランス
1968年7月にシングルとして発表された「Magic Bus」は、キャッチーなメロディとザ・フーらしいパワフルな演奏が見事に融合したポップロック・ナンバーです。バスに乗って恋人に会いに行くという日常的なテーマを扱いながら、圧倒的なエネルギーで歌い上げたこの楽曲は多くの若者に愛されました。
現在でもライブの定番曲として親しまれ、観客との大合唱が印象的な楽曲として、ザ・フーのライブパフォーマンスに欠かせない重要なレパートリーとなっています。
Substitute ~シニカルな歌詞とパンクな精神が光る初期の傑作
1966年3月にリリースされた「Substitute」は、本物と偽物をテーマにしたシニカルな歌詞と、アグレッシブなサウンドが印象的な楽曲です。3コードを基本としたシンプルながら強烈なパワーを持つこの楽曲は、後のパンクロック・ムーブメントに大きな影響を与えました。
イギリスで5位のヒットを記録し、ザ・フーの初期の代表曲として現在でも高い人気を誇っています。「偽物の代用品」という自虐的なメッセージと、それを力強く歌い上げるパラドックスが多くのファンの心を捉えています。
The Real Me ~ジョン・エントウィッスルのベースが炸裂する名曲
1973年、アルバム『Quadrophenia』に収録された「The Real Me」は、ジョン・エントウィッスルの超絶ベースプレイが光る代表的なハードロック・ナンバーです。自分自身のアイデンティティを探求するテーマを扱った歌詞と、バンド全体の緊張感あふれる演奏が見事にマッチしています。
特にジョン・エントウィッスルのベースソロは、ロック史上屈指の名演として多くのベーシストから尊敬を集め、現在でもベース奏法の教本に必ず登場する重要な楽曲となっています。
Bargain ~スピリチュアルなテーマを力強く歌った名曲
1971年、『Who's Next』に収録された「Bargain」は、精神的な解放をテーマにした力強いロックナンバーです。ピート・タウンゼントの宗教的・哲学的な思考が反映された深い歌詞と、バンドの圧倒的な演奏力が融合した代表的な楽曲として評価されています。
ライブでのパフォーマンスが特に印象的で、観客を巻き込んだ熱狂的な演奏は現在でも多くのファンの記憶に深く刻まれています。
5:15 ~青春の混乱を歌った等身大のロックアンセム
1973年、『Quadrophenia』に収録された「5:15」は、青春期の混乱と焦燥感を歌った等身大のロックナンバーです。通勤電車の中での主人公の心境を描いた歌詞と、躍動感あふれるリズムが印象的な楽曲として多くの若者の共感を呼びました。
ロック・オペラの一部でありながら、単独でも十分な魅力を持つこの楽曲は、ザ・フーの楽曲制作能力の高さを示す重要な作品として位置づけられています。
ザ・フーならでは!深みのあるバラード集
The Song Is Over ~人生の儚さを歌った哲学的名曲
1971年、『Who's Next』に収録された「The Song Is Over」は、人生の有限性と音楽の永続性をテーマにした深遠なバラードです。ピート・タウンゼントの哲学的な思索が込められた歌詞と、美しいピアノのメロディが印象的な楽曲として、多くの批評家から高い評価を受けています。
「The song is over, but the melody lingers on(歌は終わったが、メロディは響き続ける)」という詩的な表現は、音楽の持つ永遠性を歌った名句として、現在でも多くの人々の心に深い感動を与えています。
Getting in Tune ~音楽への純粋な愛を歌った美しい楽曲
1971年、『Who's Next』からの隠れた名曲「Getting in Tune」は、音楽との一体感を歌った純粋で美しいバラードです。楽器を調弦する行為を人間関係や人生の調和に重ね合わせた詩的な歌詞と、アコースティックピアノをベースにした温かいアレンジが印象的です。
ファンの間では特に愛される楽曲として知られ、「ザ・フーの隠れた宝石」と称される美しいメロディと歌詞の世界観が多くの人々の心を癒し続けています。
Blue, Red and Grey ~人生の喜びを歌ったシンプルな名曲
1975年、アルバム『The Who by Numbers』に収録された「Blue, Red and Grey」は、日常の小さな喜びを歌ったシンプルで心温まるバラードです。ウクレレをメインに使用した珍しいアレンジと、ピート・タウンゼント自身のボーカルが印象的な楽曲となっています。
「Some people seem so obsessed with the morning, get up early just to watch the sun rise(朝に取り憑かれた人々がいる、日の出を見るために早起きする)」という歌詞で始まるこの楽曲は、人生の美しい瞬間を静かに讃えた名作として評価されています。
Eminence Front ~80年代の代表的なザ・フー・バラード
1982年、アルバム『It's Hard』に収録された「Eminence Front」は、シンセサイザーを効果的に使用した80年代のザ・フーを代表するファンキーなバラードです。表面的な成功の虚しさをテーマにした現代的な歌詞と、時代に対応した洗練されたサウンドプロダクションが印象的です。
MTV時代のザ・フーの代表的な楽曲として、現在でも多くのファンに愛され続けており、バンドの時代への適応能力を示す重要な作品となっています。
However Much I Booze ~人生の苦悩を歌った切ないバラード
1975年、『The Who by Numbers』に収録された「However Much I Booze」は、アルコールに逃げても解決しない人生の苦悩を歌った切ないロックバラードです。ピート・タウンゼントの個人的な体験が反映された率直な歌詞と、感情豊かなメロディが多くの共感を呼んでいます。
人間の弱さと向き合った正直な表現は、多くのリスナーの心に深く響き、「勇気をもらった」という感謝の声が数多く寄せられている現代的な名曲として位置づけられています。
革新的なロック・オペラの世界
Tommy (Overture) ~世界初のロック・オペラの壮大な序曲
1969年、アルバム『Tommy』の冒頭を飾る「Tommy (Overture)」は、世界初の本格的なロック・オペラの幕開けを告げる壮大な序曲です。約5分の楽曲の中に、後に展開される物語の主要テーマが巧みに織り込まれており、クラシック音楽のオペラに匹敵する構成力を示しています。
この楽曲から始まる『Tommy』全体の物語は、聴覚・視覚・発話障害を持つ少年の成長と覚醒を描いた現代的な神話として、ロック音楽に新たな芸術的次元をもたらしました。現在でも多くのプログレッシブロック・アーティストに影響を与え続けています。
Pinball Wizard ~ロック史上最も有名なキャラクターソング
1969年、『Tommy』に収録された「Pinball Wizard」は、主人公トミーがピンボールの天才として覚醒する場面を描いた楽曲です。エルトン・ジョンが映画版で演じたことでも有名なこの楽曲は、ザ・フーの代表曲の一つとして世界中で愛され続けています。
「That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball(あの耳が聞こえず口もきけない盲目の子は、確実にピンボールの名手だ)」という印象的な歌詞と、キャッチーなメロディが見事に融合した楽曲として、ロック・オペラの枠を超えた普遍的な魅力を持っています。
I'm Free ~解放のテーマを歌った感動的なクライマックス
1969年、『Tommy』の物語のクライマックスを飾る「I'm Free」は、主人公が長年の束縛から解放される瞬間を歌った感動的な楽曲です。直球メロディと、希望に満ちた歌詞が多くの人々の心を打つ名曲として評価されています。
「I'm free, I'm free, and freedom tastes of reality(僕は自由だ、自由だ、そして自由は現実の味がする)」という歌詞は、あらゆる形の束縛からの解放を歌った普遍的なメッセージとして、現在でも多くの人々に勇気と希望を与えています。
The Rock ~『Quadrophenia』の壮大なフィナーレ
1973年、ロック・オペラ『Quadrophenia』の最終楽曲「The Rock」は、主人公の絶望と希望を同時に描いた複雑で深い楽曲です。イギリスの海岸にある岩を舞台に、人生の意味を問い続ける主人公の心境を壮大なオーケストレーションで表現しています。
6分を超える長編楽曲でありながら、聴く者を最後まで引き込む構成力と、ロジャー・ダルトリーの魂のこもったボーカルが印象的な、ザ・フーの楽曲制作能力の集大成として位置づけられています。
Sea and Sand ~詩的な美しさが際立つ隠れた名曲
1973年、『Quadrophenia』に収録された「Sea and Sand」は、失恋の痛みを海辺の風景に重ね合わせて歌った美しいバラードです。ピート・タウンゼントの詩的な才能が最も美しく発揮された楽曲の一つとして、多くの批評家から高い評価を受けています。
ダイナミクスを味わえる繊細なアレンジと、情感豊かなメロディが織りなす世界観は、ロック・オペラという大きな物語の中にありながら、独立した芸術作品としても十分な魅力を持った名曲として愛され続けています。
ザ・フー(The Who)の名曲紹介:まとめ
1964年、ロンドンの小さなパブ「Goldhawk Club」で産声を上げたザ・フーは、その後60年にわたって世界中のロックファンの心を震わせ続けてきました。
そして、楽器破壊パフォーマンスで音楽業界に衝撃を与えた4人の若者は、「My Generation」で若者の反抗心を代弁し、「Tommy」で音楽の新たな表現形態を創造し、「Won't Get Fooled Again」で時代への鋭い洞察を示しました。爆音で会場を揺らす「I Can See for Miles」から心の奥底に響く「Behind Blue Eyes」まで、彼らの音楽は常に時代の最先端を走り続け、後続の無数のロックバンドに道筋を示し続けています。
ザ・フーの真の偉大さは、その圧倒的な演奏力だけでなく、常に音楽の可能性を追求し続ける革新性にあります。ハードロックからプログレッシブロック、ロック・オペラから実験的サウンドまで、ジャンルの境界を軽々と越えながら、常に新しい独自の音楽を切り開いてきました。
反抗と成長、愛と孤独、希望と絶望――。ザ・フーの楽曲は、人間の普遍的な感情と体験に深く根ざしており、時代を超えて多くの人々の心に寄り添い続けています。
「ロックは死なない、それは単に眠っているだけだ」
かつてピート・タウンゼントが語ったこの言葉通り、ザ・フーの音楽は現在でも生き続け、新しい世代のミュージシャンたちに影響を与え続けています。2025年現在、オリジナルメンバーの多くがこの世を去った今でも、彼らが残した音楽的遺産は不滅の輝きを放っています。
本記事で紹介した21曲が、あなたのザ・フー体験をより豊かなものにし、ロック音楽の持つ無限の力を感じるきっかけとなることを心から願っています。彼らの音楽とともに、あなたの人生にも新しいエネルギーと感動が生まれることでしょう。
【関連記事】
オススメは?ザ・フーの名盤TOP5と初心者向けベストアルバム
ロックバンド「ザ・フー」完全ガイド:破壊と創造の半世紀、そしてロックオペラの革命